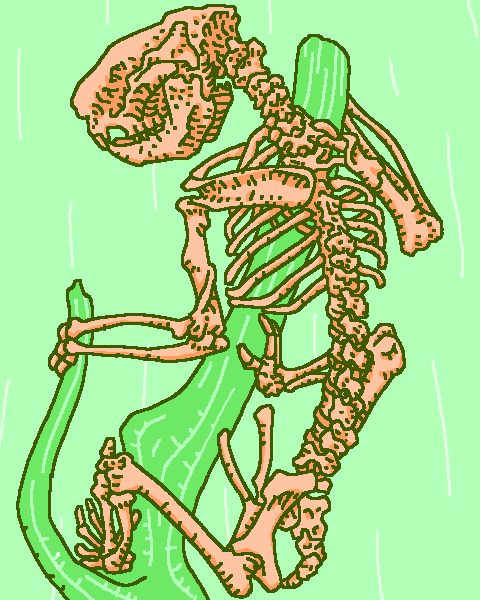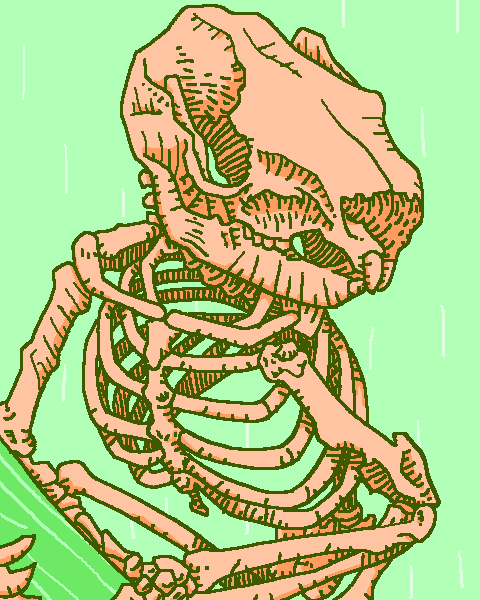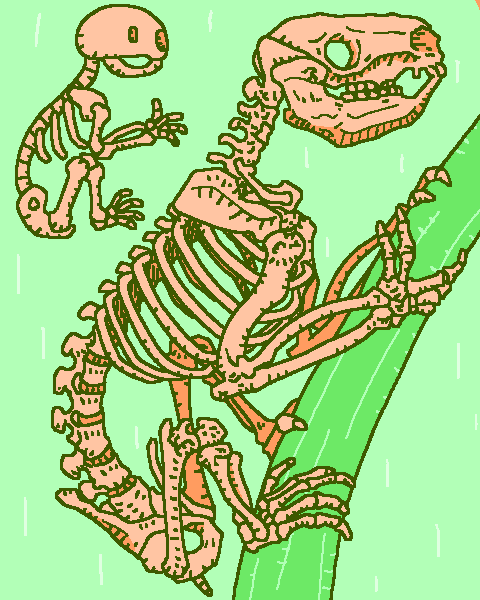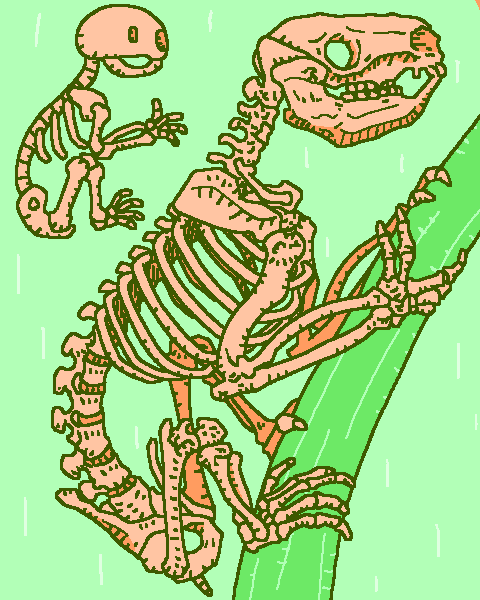
木につかまっているコアラさんの骨格です。
衝撃だったのは、私が「コアラさんのお尻部分」だと思っていたあたりが、背骨というか“腰”だったことですね。
お尻は、ともすれば隠れてしまいそうな一番下のあたりであるというのが、どうやら正解っぽいです。
───────────────
日記的な記述です。
スーパーマーケットに行き、お米の在庫はどうだろうかと確認したのですが、あいにく置いてなかったです。ざんねん。
下のお写真は本日の富士山です。

かなり冠雪が減ってしまいましたね。
1週間ほど前のようすと比べると激変したという印象です。

もう5月ですので雪が溶けてしまうのは当たり前ではあるのですが。
───────────────
以下はラジオ日記です。
NHKラジオ第1「子ども科学電話相談」を聞きました。
「動物園の飼育員さんは苦手な動物っているの?」という質問が面白かったです。飼育員さんとはいえ人間ですので苦手な動物はいるのでは。確かにその通りです。
回答者は埼玉県こども動物自然公園の副園長、田中理恵子さん。田中さん自身は苦手な動物は特にないとのこと。これはさすがだなと思います。質問を寄せてくれた子も特別に嫌いな動物はいないけど、しいていえばピパピパという平べったいカエルはちょっと怖いということでしたけど田中さんもそれはちょっとあるということでした。ピパピパは最初に目にした時に誰しもビックリすると思いますので納得です。
私自身は寄生虫とかの細くて長くてたくさんニョロニョロしているのが苦手です。しかし調べてみるとハリガネムシを手の上に乗せている人がいるんですよね。すごいと思います。理屈で考えればヒトの手の上に乗せたところで実害はないとわかるんですけど、なんか意志を持ってそうでイヤかなって思います。
それで肝心の質問の核心部分なんですけど意外と普通でした。やっぱりどうしてもダメな動物がいる飼育員の人もいるのだということでした。代表的なのはヘビとかゴキブリであるようです。なるほどね。
恐竜の先生の小林快次さんもゴキブリはダメっておっしゃってましたし。一般の人間からすると特殊な人達だと研究者のことを捉えがちですけど感覚としては普通なんだなと知れるのでありました。
しかし動物園という環境下で仕事として触れ合っていくうちに、なれたりすることもあるよ。ということでした。
───────────────
NHK・FM「現代の音楽」を聞きました。
今日から3週にわたって大阪万博について特集なのだそうです。非常に良い企画。本日は概観ってことで来週からゲストを迎えて音源を聴いていくということでした。とても楽しみです。どうやら解説の白石美雪さんは去年に万博会場跡に行って太陽の塔の内部も見てきたようでありまして、思いの強さも伺えます。白石さんが番組内でおっしゃっていた通り、大阪万博エキスポ70が現代音楽のひとつのピークをそのまま映し出したお祭りだったということは疑問のさしはさまる余地ないことであると思います。これは番組前任の西村朗さんも熱っぽく語るのを過去に聞きました。西村さんは大阪の人でその時期高校生だったのでとりわけ純粋な感性で受け止められた人だと思いますが、幸いにも音源は残っておりますので当時を知らない、実際にその場になかった人でも学べることはそれなりにあるぞってことだと思います。
聞いた楽曲としてはこれも手応えのあるものが多くてというかそんなのばっかりでしたけど、まずは 松村禎三さんの「祖霊祈祷」の一部分を聞きました。スクリャービンみたいな感じでしたかね。圧倒的でした。未来と土着がくっついたイメージですかね。素晴らしかった。
それと私も大好きな電子音楽作品。一柳慧さんの「生活空間のための音楽」も一部分を聞きました。
三善晃さんの「祝典序曲(開会式)」 が超絶スペクタクルで素晴らしくて心が打ち震えましたんですが、三善さんの想いを綴った文章の紹介を聞くにつけ深いものがありました。敗戦から四半世紀の日本の当時において戦争とお祭りを重ねつつ人の生命や文化の死を直視する視点というか厳粛な思いで作曲したんだなと思いました。
ここまで記述した音楽それぞれに思想がありますね。できればもう少し深く知って理解したいなと思います。