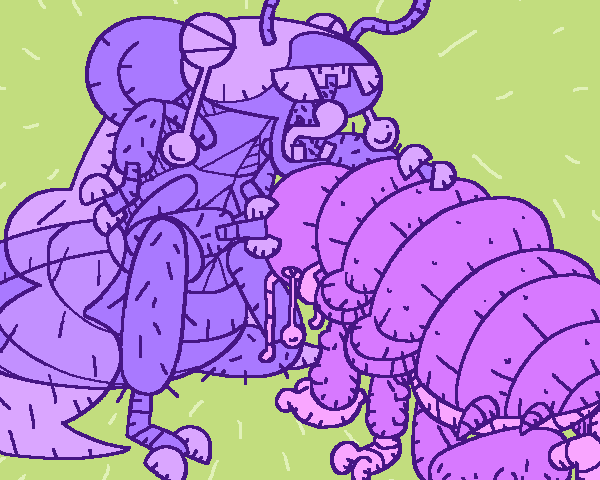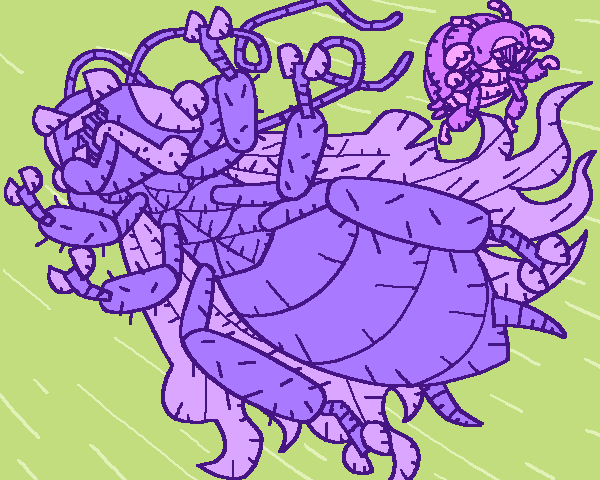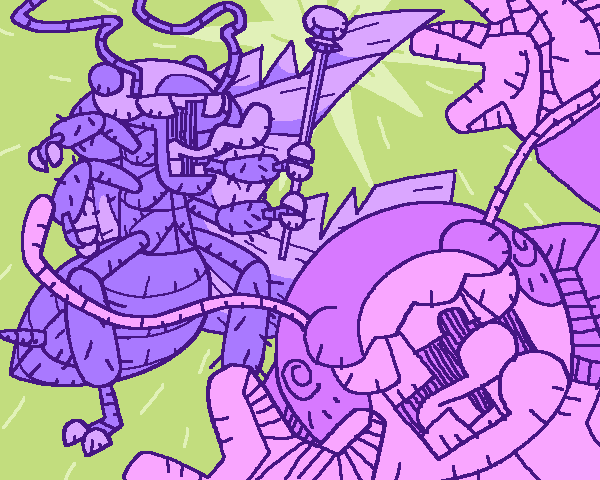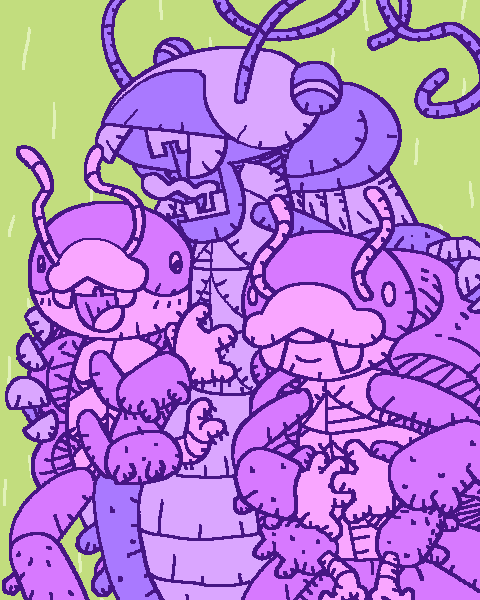
ヒーローアニメなんかによくあるラストシーン的なイラストです。
「よかったよかった」とか「一件落着」みたいな感じですね。
───────────────
ラジオ日記です。
俳優の六角精児さんご選曲による鉄道ソングの数々を聞きました。
パット・メセニーさんのバンドの「ラスト・トレイン・ホーム」という曲では列車が線路の上を走る音をブラシ奏法で見事に再現していて驚きました。
エルヴィス・プレスリーさんの「ミステリー・トレイン」ではギャロッピング奏法の解説あり。私もちょっと試してみたことがあるんですが歯が立ちませんでした。いつか弾けるようになりたいです。具体的にはビートルズでのジョージ・ハリソンさんによる「オール・マイ・ラヴィング」の間奏です。この曲はレノン氏による伴奏の3連譜もあのニュアンスを出そうとするとかなり難関で。土屋昌巳さんなんかはわりと簡単に最初から弾けたとか聞いたんですけど。言いぶりからするとまだ地元・富士市にいた頃だと思うんですよね。
別に番組内ではビートルズはかからなかったのですが、モンキーズがかかりました。
「ラスト・トレイン・トゥ・クラークスヴィル」。
詩の内容を六角さんから教えてもらえました。反戦歌のおもむきもあるんだそうです。
またよく言われることですが、「モンキーズは演奏できたのか?」という話題についてもひとくさりありました。これについてはジ・アルフィーの坂崎幸之助さんのラジオを録音したものがネットの動画サイト等で参照できると思いますが、その内容で信頼の置ける演奏者の方がかつて彼らの演奏に随行した際の証言がございまして、それによると「3コードの曲なんかはけっこうウマい」だそうです。ただポップス寄りの若干難しいコードになると弾けないのだろう、音源を流して当て振りもあったのかな、みたいな感じのおっしゃり方だったと思います。主旨としては意外な演奏力という文脈だったと思います。
ウッディ・ガスリーさんの曲もかかりました。フォークソングにおけるプロテストソングの意義というか、重みというか、六角さんの思いとしては、こここそが本質ではないかと熱弁されていました。
あとローリング・ストーンズにおけるミック・テイラー氏の名演も聞きました。これはロックとかを聞く人ですと誰にも否定できないというか「ありがとうございます!」って拝聴するしかないですよね。ミック・テイラーさんの後ろに万単位のギタリストが「オレもこれはコピーした」っていう勢いで連なるといった存在です。
以上のような感じでした。六角さんは舞台のお仕事のため、番組を中座して仕事場に向かったのですけど、プロテストソングの来歴のあたりは聞き応えがありました。
番組の最後の方で、ザ・ブームの楽曲「中央線」を聞きました。
番組を聴き終えた後、個人的な音楽聴取としてザ・スターリンの楽曲「STOP JAP」をネットの動画サイトで聞きました。歌詞の中に「中央線はまっすぐだ」という一節があるのです。
やっぱりくつろぎますね。家に帰ってきたような思いがいたします。
近況に入りますが、非常にたくさんのシンセポップを聞いて整理する活動をイラスト作成のかたわら進めているわけですが、ちょっと疲れましてですね。
きのうの晩は手持ちのパンクロックソングを片っぱしから聞いて心の安静を得ました。そんな最近です。
本日のブログ更新の後はモーターヘッドによる「トレイン・ケプタ・ローリン」のカバーを聞こうと思います。