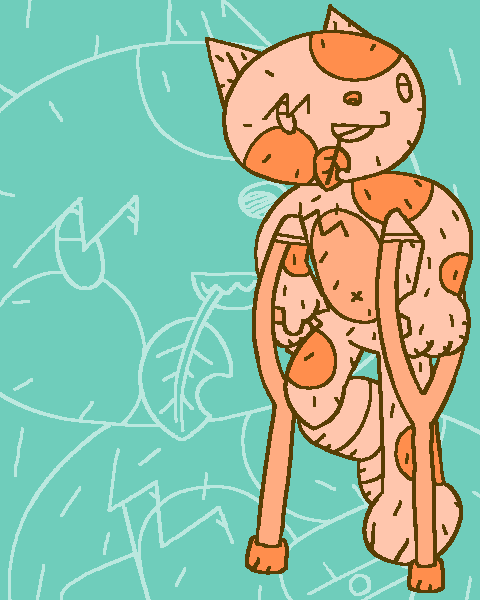
きのうの「サブマリンシュートで骨折」の続きです。
ポッキリいっちゃった子なんですけど、その後しばらく松葉杖を使っていました。
周囲の子たちの間に「小学生らしからぬカゲがある感じ。なんかカッコいい」みたいな評価が顕現しまして「なんとも言い難いストーリーを背負ってる感じ。憧れる!」みたいな間違った思想が立ちあらわれる始末。
みんなちょっとどうかしている感じでした。マンガのマネしてケガしただけなのに。
しかしそんなバカさこそが小学生なのかなっていうのも、ありますでしょうかね。
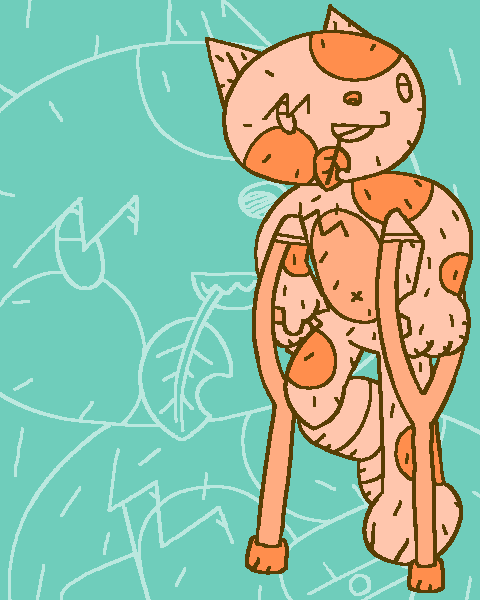
きのうの「サブマリンシュートで骨折」の続きです。
ポッキリいっちゃった子なんですけど、その後しばらく松葉杖を使っていました。
周囲の子たちの間に「小学生らしからぬカゲがある感じ。なんかカッコいい」みたいな評価が顕現しまして「なんとも言い難いストーリーを背負ってる感じ。憧れる!」みたいな間違った思想が立ちあらわれる始末。
みんなちょっとどうかしている感じでした。マンガのマネしてケガしただけなのに。
しかしそんなバカさこそが小学生なのかなっていうのも、ありますでしょうかね。
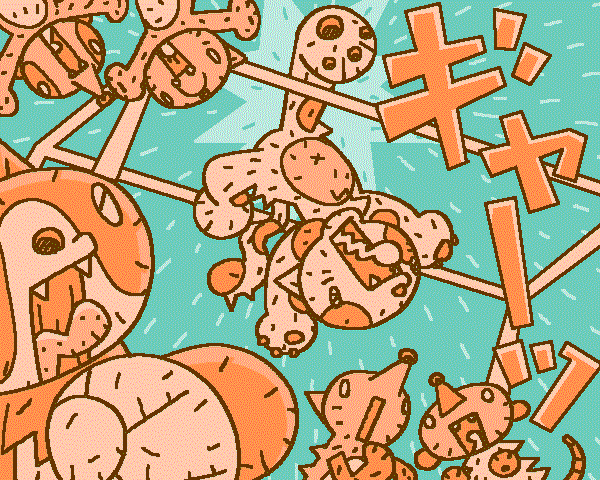
タイトルについてですが、きのうまでは「こども」という全部ひらがな表記でしたけど、今日と明日はちょっと年齢が高いので一部を漢字にしました。
小学校の放課後の時間。
みんなでサッカーをしている時に秘技「サブマリンシュート」をくり出した男の子が、ボールではなくゴールポストのバーをけってしまって足の骨がポッキリいってしまった。
という事件をとらえたイラストです。
私が小学生の頃の記憶なんですけど、その場を見たわけではないです。私はそんなに活発な子ではなかったので早く帰宅するタイプでした。
運動が得意な子がその能力を生かしてしまったがための骨折だったのですね。
わからない方も多かろうと思いますので解説いたしましょう。
「サブマリンシュート」というのは「赤き血のイレブン」という原作としてはマンガですけど、私の世代的にはアニメっていうか当時の言い方でいうと「テレビまんが」ですね。「アニメ」って割と新しい言い方ですから。
「赤き血のイレブン」は当時としてもちょっと古い作品だったんですけどテレビの再放送で放映されていたのでした。再放送って毎日同じ時間にやっていたりしますから子どもとしては嬉しいのです。
毎日連続してテレビまんがワールドにひたりきってしまい、あげくには「オレにもできる!」と思ってしまったのかもしれません。
つまり「赤き血のイレブン」に出てきたムチャな必殺技が「サブマリンシュート」です。ボールをけった後に半身を反りかえらせるという、それをしたところでどうなるんだろう。わかったようなわからないような必殺技ですけど、アニメですから特殊効果がピカーっみたいな感じで「そうか、必殺技なんだ!」ってムリヤリ納得させられるという作りなのでした。
もう1点、本日のブログ用イラストのネコちゃんのポーズについても解説しておきたいと思います。
ゴールポストの上部のバーをけっていますけど、これはウソです。見栄えを重視して私が創作しました。小学生ですのでっていうか普通の人間ですから高い位置なんてけれません。低い位置にある横のバーでモッキリいっちゃったみたいです。
少し前に私はネット上の話題としてマンガ家の「すがやみつる」さんが、ご自身の創作における思い出を振り返るという記述を目にしました。
いわく「最初の頃に手がけたマンガの主人公が“見せ場”において逆立ちするようなポーズであったため、それ以降のヒット作においても逆立ちポーズを編集部の人から求められた」というようなことでした。
「すがや」さんは富士市生まれの方ですので、私も偉大な先達にあやかる形で「さかだちポーズ」を実習してみたというわけです。うまくいっておりますでしょうか。
ちなみに私の住む町内会の自主防災会で用意してある無線機は「すがや」さんに関係のあるお店で買ったものです。免許の更新も依頼してあると思いますが、現在も続いているかまではわかりません。自主防の中で引き継ぎがうまくいっているかっていうお話なんですが、ともあれお店の方は古くからあるのでおそらく私のところの町内会だけではなくもっと広くお世話になっていると思います。発災からしばらくは携帯電話も使えないだろうということで買ったんですよね。

1歳になったくらいの小さな子が、朝の起きたあと踊ってくれるというその光景を想像して描いたイラストです。
こちらもNHKのアナウンサーの方の育児エピソードなんですけど、きのうまでとはまた違った方のご家庭における朝の風景だそうです。
寝起きが良い子なのでしょうか。まだちゃんとしたダンスをするということではないと思い、ピョンピョン、パタパタしている感じにしてみました。
───────────────
きのうはすみませんでした。後半は全然「こどもライフ」じゃなかったです。
還暦にも近い私による「音楽ライフ」になってしまいました。
個人ブログとは言え、たびたびの暴走。暴走老人です。面目次第もございません。以後も度々暴走すると思います。
───────────────
ラジオ日記です。
きのうの夜のNHK・FM「クラシックの迷宮」ではルイジ・ノーノさんの音楽を聞きました。まとめてちゃんと聞いたのって私は初めてです。
全体を通して感動しました。晩年は静かな作風に進化、深化して行ったのですけど、そこへ至るまでの激しい作風も良かったです。
イタリアの作曲家なのですが、スペイン内戦で殺されてしまった詩人にまつわる作品があり、それを聞きました。あとは「不寛容」に抗う曲、テープ音楽、晩年の静かな作風、これが遠くからかすかに語りかけるような、その声との出会い、みたいな感じだったと思います。
私は映画「ミツバチのささやき」を思い出しました。スペイン内戦の後の気持ち的には分断されてしまった人々、大人たちが内心を素直に表現できない抑圧下。小さな女の子は精霊に出会う。極端に「話す言葉」が少ない静かな映画なんですけど、その時の夜のイメージ。不思議な体験の後に「私はアナよ」と窓の外の夜に向けて話しかける、自我を表明するみたいなお話。ノーノさんの「遠くから語りかけるような声なのか意識なのか生命なのか希望なのか」そうしたものとの出会いの音楽と重ね合わせました。
また指揮者で作曲家のパウル・デッサウさんという存在を初めて知りました。
全然関係ない話になりますが、EBM(エレクトロニック・ボディ・ユージック)とかインダストリアル・ロックのバンドである「DESSAW」の「Exercise in Tension」というアルバムを思い出してしまってネットの動画サイトで聞き直しました。私が23歳の時に非常によく聴いた音楽です。テクノロジーを使いながらも粗野で乱暴なところが当時はとても良いなと感じていました。聞き返してみると普通にロックっぽい魅力も多分に備えていた音楽だと気付いたという次第です。懐かしいですね。EBM。私自身はインダストリアル・ロックっていう呼称は使いませんでしたけど。本当に全然関係ないお話でした。ラジオ日記に戻します。
今朝は同じくNHK・FM「吹奏楽のひびき」を聞きました。高昌帥さんの音楽をご本人をスタジオに招いて聞きました。下野竜也さんは高さんの曲を指揮することもあるそうでしてその録音も聞きました。
高昌帥さんというお名前は「こう・ちゃんす」と読むのだそうです。良い名前ですね。ロックバンドのドアーズの「Take It As It Comes」という曲の邦題が「チャンスはつかめ」っていうかなり良い邦題がついているんですけど、すごい好きな曲なんですけど、ラモーンズもカバーしたんですけど、それはさておきまして、高さんの曲ですが、「ウインドオーケストラのためのマインドスケープ」という代表作の一つというご紹介でしたが確かに非常に良かったです。下野さんの指揮も焦点のあった聞く人を引き込んでいく手に汗握る展開でした。それと最後の方で聞いた「吹奏楽のための協奏曲から第5楽章」も良かったです。
つづく番組「現代の音楽」。4人組コンサートの後半。金子仁美さんの3Dモデルを作曲法に用いた曲シリーズの新作。恒星を描写したというものだったと思います。解説の白石美雪さんのおっしゃることが実に的確に金子さんの仕事を言い表しているなと思いました。曲としては面白い音の連なりが現れては転換していくという印象を持ちました。
池辺晋一郎さんの曲も聞きました。西村朗さんが亡くなった日に完成した曲、そうとは知らずに完成させて訃報は翌日に知ったということでした。西村さんの霊に捧げるとのこと。ハーモニカとピアノの組み合わせ。非常に良かったです。詩人の大手拓次さんの「ちろ そろ ちろそろ」という詩をもとにした曲でした。冒頭は本当にハーモニカで「ちろ そろ ちろそろ」とそのまま歌っているようで笑ってしまいましたがそこで開いた胸襟に豊かに響くハーモニカの音色が胸の内をふるわせていくような音楽だと感じました。
池辺さんがどれくらい「詩をもとにした曲」を作っているか私は不案内ですけど、去年に「君は土と河の匂いがする」という曲を聞きました。非常に具体的な題名です。あとで知ったんですけどこれも詩が元になっているのでした。私はそうと知らずに題名のイメージのまま聞いたんですが、ちょっと不安な感じで「君」の中に入っていくんですけど、「君」のその奥に触れるたびに「じわ〜」っていうような温かい感情が湧きあがり、またさらに深い場所に進む。というような印象を持ちました。この際の「じわ〜」っていうところがスゴく良くて心に残る曲でした。あとで元になった詩をネットで調べて読んでみて「ちょっと違ったかも」って思ったんですけど、私としては「相互に理解するその喜び」みたいなことで思っておこうかなと思います。池辺さんが何かの番組で「現代音楽は推理小説を読む人に向いていると思う。この曲は何かな?って探るような人に」みたいなことをおっしゃっていたのでギリギリセーフかなって思います。
せっかくなんでもう1ヶ書いておこうと思うんですが同じく池辺晋一郎さんの「ユーフラテスの響き」という曲もネットの動画サイトで聞きました。ユーフォニアムとピアノの曲です。たしか番組「現代の音楽」で微分音をユーフォニアムで鳴らすっていう回を聞いた後に「池辺晋一郎さんにユーフォニアムの曲があったような」と、微分音は関係なくなっちゃいますけど、そうして探して聞いてみた曲です。ユーフラテスっていうくらいですので大きな川を思い浮かべて聞くんですが、やはりユーフォニアムの豊かな柔らかい響きを感じられて、大きくゆったりとしたものを感じられて嬉しいんですけど、ピアノの音がなんだか垂直に突き刺さるような気がしてしょうがないんですよね。最初は川岸に生えている葦などの植物のまっすぐな感じなのかなって思ったんですけど、いやこれは違いそうだと思いました。ちょっと調べてみたところ、ユーフラテス川の流れるその辺りで紛争が絶えないと。そうした現状に心を痛めてっていうことみたいです。納得しました。今ネットで聴けるピアノの演奏をしてらっしゃる方はうまく演奏できているなと思います。今も改めて聞きなおしてみたんですが、思っていたよりもユーフォニアムの音の列というのはシンボリックな響きが随所に感じられて、やはり動きがある。決して静かな流れで満たされているという感じではないのかなと気づきました。「渦(うず)」みたいな感じですかね。すべての人が戦禍に巻き込まれることなくその生を全うして欲しいと心の底から思います。
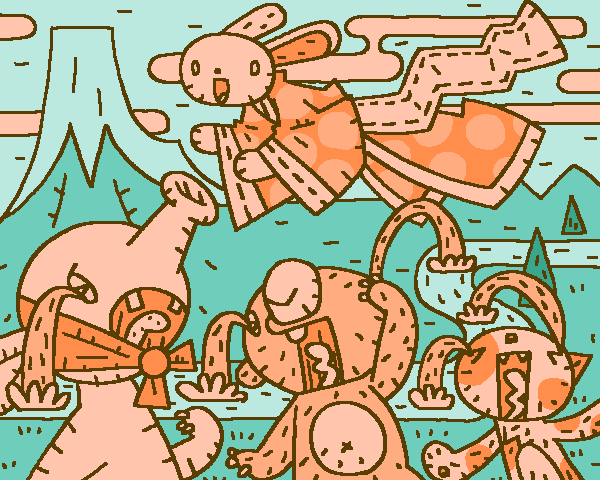
これはちょっと私らしいバカバカしくもハッピーなイラストが描けたんじゃないでしょうか。上の方にお姫様が浮かんでいて、下の方で動物たちが泣いています。「なに描いてんの?(いい大人が)」って感じでありまして、ウマくいったと思います。
解説いたしましょう。
これは富士市に伝わる「かぐや姫」のお話を元にしたものです。
きのうまでのエントリで「潤井川(うるいがわ)」の話題が続きましたので、挟みこんでおこうと思いました。
富士市における「かぐや姫」って、全国的に伝わる主流のお話とは少し違っておりまして、「月に帰るかぐや姫」っていう最後の部分ですけど、「富士山頂に帰るかぐや姫」っていうことになっています。
かぐや姫は富士山の住人だったというか。化身、権現とかそんな感じなのかもしれません。
付随する描写として、「かぐや姫がいなくなっちゃうって!」と聞きおよんだ村人たちが心の平衡を失って泣き出すにいたる。その涙が集まって「潤井川(うるいがわ)」になったよ、みたいなことが描かれております。
私の感想としては、かぐや姫の伝説が伝わる原田の地域と、潤井川が流れるその流域ってちょっと離れてますので、どうなんだろうかって思いもございます。
むしろ原田に直近の「滝川」の方がそれっぽいなっていう気がしますが、別に古い昔に成立したお話に今の私が文句をつけても仕方ないでしょう。
そうだ。ついでですので、撮ったは良いけど使いどころがわからなかった画像をご紹介いたしましょう。
滝川の川沿いの道のお写真なのです。原田より北に移りまして、地図でいうと「三ッ沢大橋」っていうところです。

画面中央に小さなトンネルがあります。
トンネルの上にはちょっと大きめの道路が通っています。地元的には「富士見台の南側の道だら(“だら”っていうのは方言でありまして、この場合「ですよね」といった同意を求める用法)」って感じ。
滝川はこのあたりですと深い谷の底を流れておりまして、左側の地面が下がっている感じが見て取れると思いますが、その先の下の方になります。このアングルからですと見えません。

上の画像に特別な意味はないんですけど富士山の姿をお見せしたくて掲載いたします。頭がちょっと見えています。

これです。
「MILKY」って書きたかったんじゃないでしょうか。惜しいですね。一文字多かったようです。
もうずいぶん前からある落書きですので、おそらくこれを書いた人も今ではかなり良い年なんじゃないでしょうか。
落書きは犯罪ですけどね。念のため。
伊集院光さんがやっているラジオ番組でも短期間にこうした「違法であるがちょっと笑える落書き」の企画があったことを思い出します。
しかしおそらく自分たちのチーム名をトチるってなかなかですね。カタカナで書いておけば良かったのかなって思います。
本日は以上です。ありがとうございます。
───────────────
ラジオ日記を短く加えておこうと思います。
NHKラジオ第一の午前中の帯番組「ふんわり」を聞きました。俳優で音楽家の六角精児さんと、イラストレーターでありデザイナーであり、音楽活動もされている安斎肇さんがご出演。楽しいお話を聞きました。
おふたりのお父様のお話も聞けました。どちらもひとつのことに熱意を傾けて過ごした人生だったご様子。真面目な人柄が伝わってはきましたが、チャーミングな面も備えていたのかなという感想でした。
音楽的にはライ・クーダーさんの曲を聞きました。ミシシッピ・ジョン・ハートさんの名前なんかも出てきたり、囚人の人たちが敷設していったアメリカの鉄道建設における労働歌のお話、平たく申しまして戦前ブルースの一部でしょうか。そんな局面もあったと思います。
それと安斎肇さんの歌唱を2曲聴きました。どちらも意外なほど良かったです。特にロック調の曲の最後の方におけるフリースタイルな部分は力強いものというか、普段のおしゃべりの様子とはまた違う発見がありました。