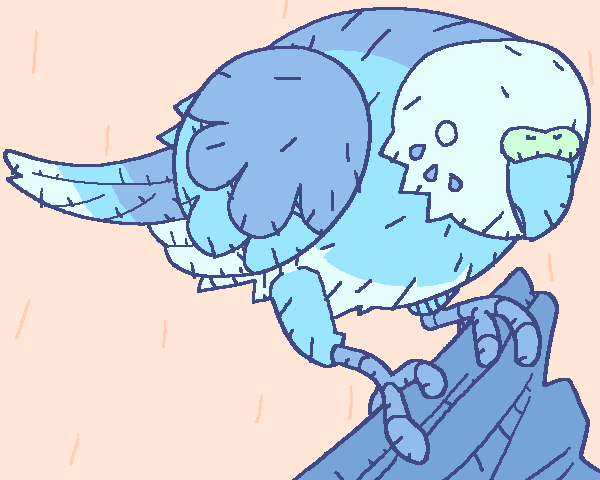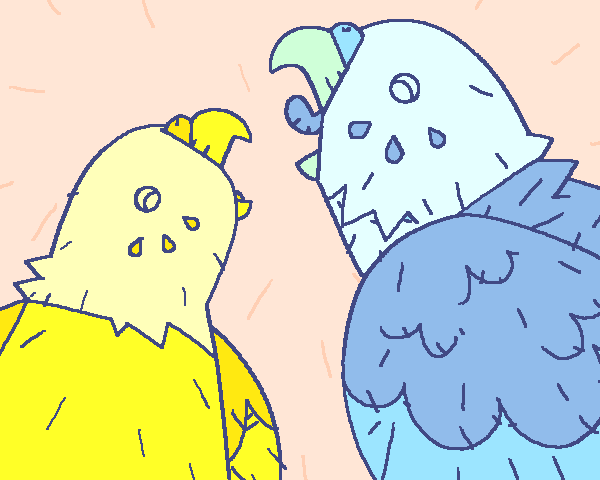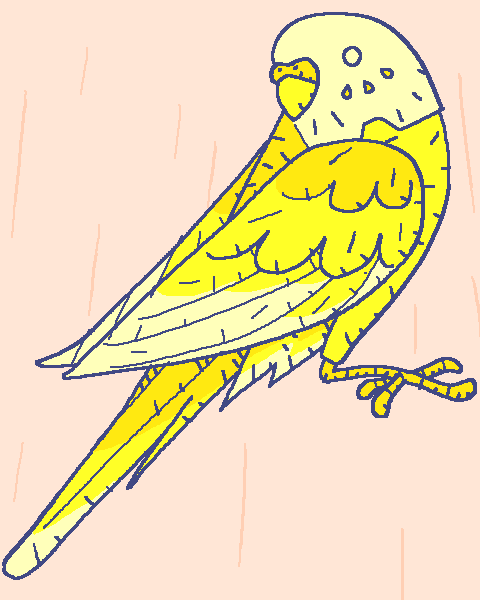
後ろをふり返っているインコさんのイラストです。
───────────────
午前9時より町の公会堂で会議がありました。
町内会の活動。
いわゆる「市道化委員会」です。
会議としては今年度の最後の集まりでした。
明日は町内の全組長さんたちが集まる組長会議があるんですが、その場において「市道化委員会」としての活動の報告と承認という手続きがたぶん必要なのです。
「市道化委員会」は町内会に接続する諮問機関みたいな位置付けなのです。独立しての決定権みたいなものは持っていないんですね。
そんなわけでして、会議の議題は「今年の実績(のまとめ)」と「来年度の予定」についての確認でした。
これで今年度の会議は終了ですが、来年度に工事を予定している区画についての実況検分を市役所の人たちと行いたいという気持ちです。来月くらいに。
準備だけ済ませておいて、来年度が始まったらなるべく早い時期に工事を始めたい。しかしそれについては地権をクリアできていない箇所が残っているんですが、すでに弁護士の先生に動いていただいているので、まぁおそらく問題解消への運びに持っていけるのではないかという見通し。
以上の条件で市へと道路を移管していこうというかまえです。
そうなるともう来年度の「市道化委員会」としての活動はあまりないのではと期待しています。予算の都合で他の案件には手をつけられなさそうなのです。弁護士費用と工事費用。そして測量費用などが必要なのです。大変。
おそらく来年の同じ時期くらいに残る区画の実況見分を市役所の人とするんではないかと思っていますけど、これは私が個人的にそう思っているだけですし、かなり先のことになります。
早く済ませたい気持ちはあるものの、お金の問題もあるので、なかなかそうはいきません。
───────────────
ラジオ日記です。
「世界の快適音楽セレクション」を後半1時間ほど。
レジデンツの楽曲「Sitting on the Sand」を聞きました。
スネーク・フィンガーさんの弾くギターが聴ける曲だということでした。明るい音色で演奏する暗い曲調だというご紹介。選曲者の湯浅学さんもゴンチチのおふたりもレジデンツはお好きなので話もにぎやかに盛り上がっていました。
私の感想としても楽しかったです。
他には、大竹伸朗さんの78年から録音していた素材。80年に発表したデビュー・アルバム。なんだかさっぱりわからない音楽。Jukeというバンド名義での「Office Party」。この曲は最高でした。弾力と打撃音。エコー効果が呼び寄せるパースペクティブ感。なんでも膨大な録音素材があるそうで。私としては大竹さんが音楽活動をしているなんて全く初めて知りましたので全てが驚きでした。
コンラッド・シュニッツラーさんの作っていた「音の彫刻」的な活動を思い起こしました。あの人もとにかく量産できる人で。きっと音の配置であるとか組み合わせに関心がおありであって、日記のように音を作っていった人なんではないかというのが私個人の見立てです。私はシュニッツラーさん音源については数としてはけっこう持っているんですが、前述の通り全作品数が膨大ですので、どうでしょうか。1割くらいは押さえているのかっていう感じですね。
他にはデヴィッド・シルビアンさんとデレク・ベイリーさんの共作。初めて聞きました。これも良かったです。「She is Not」という曲でした。
*** *** ***
ラジオ番組「文芸選評」も聞きました。俳句の日。
兼題は「白梅」でした。いやー。あちこちで梅が咲いているのを見かけますけど、うれしいですね。春らしくて。心がはずみます。
そんな心境で寄せられた俳句を聞いていくわけなんですが、ある句において「白梅」と「学徒」という言葉を使った作品がありました。戦時中のことを詠んだのでしょうか。沖縄戦における「しらゆり部隊」は有名ですが同じような活動として「白梅学徒(隊)」という存在があるそうです。その隊員であった中山きくさんという方が1月に亡くなられたということで、私はちょっとそのことを思いました。平和への希求ですね。大事なことだと思います。
───────────────
ちょっと長くなっちゃいましたけど、上で「デレク・ベイリー」さんの話題を書きました。実はきのうの夜から今朝にかけてインターネット上の「ちくまWeb」というサイトにおいて大友良英さんの若かった頃についてご自身が振り返る内容の文章を読みました。連載企画で10数本あるのでそれなりに読み通すのにも時間がかかります。その中でやっぱりデレク・ベイリーさんの作品についての思いであるとかが書かれていて、これは相当にこだわってるんだなと理解したんですが、その他の具体的な活動についても知りまして。かなり驚きました。
大友さんがミューズ音楽院という学校で行われていた、高柳昌行さんの週1セミナーに通われていたというくだりです。
以前に当ブログにおいて私が過去に千駄ヶ谷の古いアパートに住んでいたことがあると書きましたけどそのアパートからとても近い場所なのです。ミューズ音楽院って。直線で120メートルくらいです。
私が住んでいたアパートよりも代々木の駅に近いのですが、ちょっと奥まった場所にあるので建物に近づいた経験はないです。しかし表の路地は非常によく通っていたのでビックリしました。
高柳さんの教室はミューズ音楽院の教える内容からは独立したものだったようです。どうやらその後に場所を変えてセミナーをやっていたのかなという感触。そちらは四谷の近所だったというお話を南佳孝さんがラジオ番組で言っていたように思います。四谷と千駄ヶ谷ですからどちらにしてもそんなに離れていませんが。
それとこちらも初めて知りましたが高柳さんが四谷の若葉町に住んでいたっていうことですね。
この町内に美味な「たい焼き屋さん」があって、店名「わかば」っていうんですけど、そこのたい焼きをサラリーマン時代に写植を取ってくるお使いの帰りなんかによく同僚の分なんかを頼まれて大量に買って帰っていた経験などを思い出しました。そうか、あのへんだったんですね。などと色々と納得したりしました。
高柳さんが教えていた内容というのは非常に厳しく基本を叩き込むっていうものだったようですけど、それを知って南佳孝さんがご自身の糧としていけたというのも納得しました。何かに特化したものではなくてもっと応用していけるものだったんではないかと思いました。普通に考えると南さんと高柳さんってつながりそうにありませんよね。