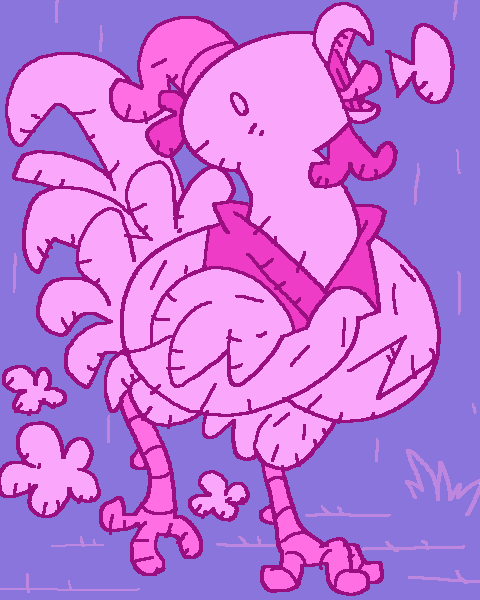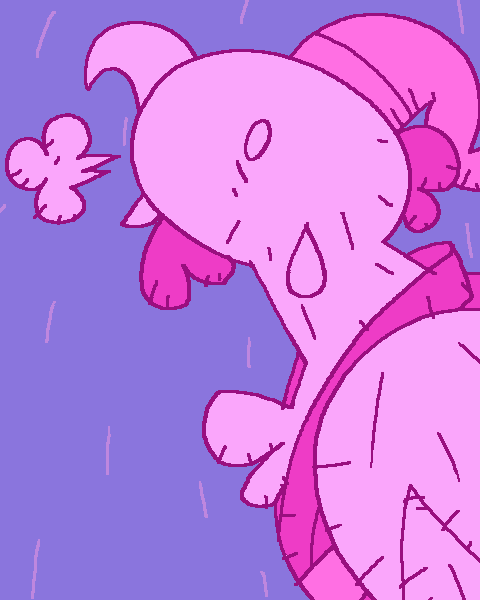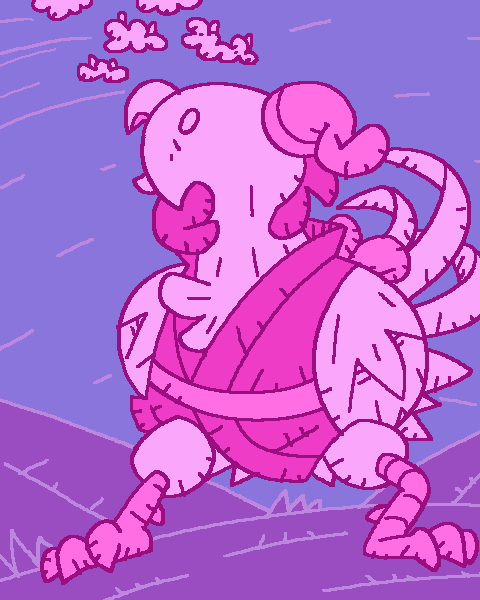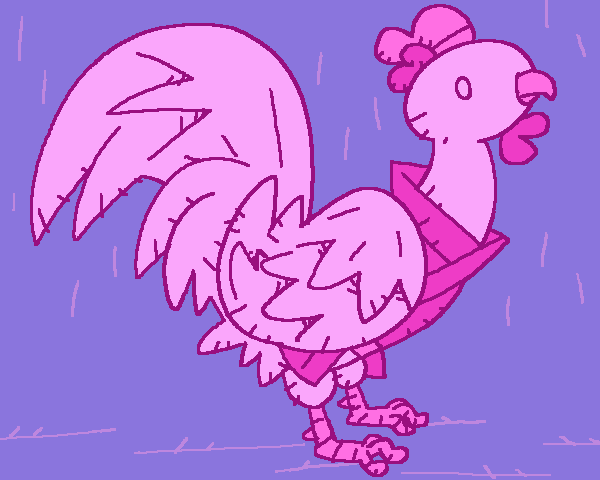
きのうの内容と関連するんですけど、ハンス・アイスラーさんの音楽を聴きました。ネットの動画サイトで。映画の分野での仕事を確認したかったのです。
ちょうど都合よく、動画をまとめたものがありましたので有り難く拝聴。どれも短くて確認作業にはぴったり。
意外な収穫としてはトラウトニウムですね。これは私みたいな電子楽器ファンには有名な楽器。オスカー・サラという方の使用で有名という認識でしたけど、今は正確に「オスカル・ザラ」って呼ぶんだそうです。いろんな動画を見ましてもモロにそう呼ばれておりまして「あらマそうなんだ」と認識を改めました。ご本人の演奏も数本の動画で確認。
アイスラーさんの映画音楽でのザラ氏の演奏は割と「電気の鍵盤楽器」の域を出ないものに聞こえました。がしかしアンプを介してオーケストラと合わせたっていう感じで、その日に使用したアンプの特性なのかハリのあるアタックの強い良い音。オーケストラに対抗するって意味でもよくできていたのかなと感じました。
それとは逆に、おそらくご自身のスタジオでの演奏はもう少し電子楽器としての可能性を推し進めたもので、かなり意欲的なパッチを組んだ音色、おそらくディレイもかましたりしていて、ザラ氏の頭の中のイマジネーションを垣間見れるものだったかなと思います。これは有意義でした。かなり晩年の演奏であるようでしたがイカした電子のおじいちゃんでしたね。グレートです。かなり長命な方で90をすぎた2000年代に亡くなったという。割と最近までご存命だったんだなって知れて、これもまた良かったです。
───────────────
ここからラジオ日記に入っていくんですが。今日はもう朝から「現代の音楽」を聞くぞ!っていう意気込みにあふれてまして。本日の放送予定の内容というよりは先週の感動の余韻ですね。ぶり返してきまして。
グレツキさんの交響曲第3番「悲歌のシンフォニー」を動画サイトで視聴。曲としてどうっていうよりもやっぱり女性ボーカルの美しさ、はかなさに引っ張られちゃって大変です。全部聞くと50分くらいあるのかって知りましたけど、それが分かると「これは良い50分だな」って思えてきちゃいます。
順番が前後しますけど、その前に実はシェーンベルクさんの「ワルシャワの生き残り」も聴きました。こちらも先週のラジオ番組「クラシックの迷宮」で聞いて衝撃的だったんですけど。まぁどちらの曲も戦争という大きな物語って言っていいのか、圧倒的な悪行を前にしてシェーンベルクさんも作風の角度を修正せざるをえなかったっていう解説だったかなって思うんですけど、聞いている方も厳粛に受け止めざるをえないような、非常な緊張感というか圧力というか。マとにかくレイシズムの行き着く先という歴史的な事実をこれはもう未来永劫、折につけ確認していく。それが正しい行いなのかなって改めて思いますね。
私が思うにレイシズムの構造って二層あって、上の方では経済的な効率、下の方では無知や思い込みにかられる性急な差別感情。おそらく両輪どちらもセットなんだろうなって考えています。この“両輪”っていうのが一度はずみがついちゃうと止まりにくいんですね。恐ろしいですよ。そういう二層ある大きな構造って公害による健康被害であるとかそんなものにも共通するのかなともモヤモヤと考えたりしています。
戻しますけど「現代の音楽」。気づいたんですけどもう時代的には1970年代なんですね。こりゃもうつい最近だなっていう気もしますし、パンクロック史的に言っても重要な年代なんですけど、今日はペルトさんのね。「ペルトのティンティナブリ様式」。こちらを西村朗さんに紹介していただきました。
鈴を振ったときに発生する基音、倍音。「鈴」っていうのは非常に豊かな倍音構造をしていると思います。そこから出ない音響。その中で発生する音楽っていうんですか。最初の原初的な作品から、年を追うごとにより豊かになっていくものの、ひとつの響きを大切にしていく姿勢。そのへんはよく理解できたと思います。また美しかったですね。「けっこう宗教的だぞ」って思っていたところに、「さらに宗教的になっていきます」みたいなことを西村さんがおっしゃって「更に行くのか」って思いましたけど実際そうでした。
自分の存在を消して、音を配するという姿勢であるのだというお話でした。
先週、今週と「単純性」をテーマに、地域としてはポーランドとかエストニアとかのソビエト近隣からのもの。そんなことを学んだんですけど、印象としては「美しさ」というのが残ったのかな。って思います。ココロが洗われるような、そんな日曜の朝になりました。