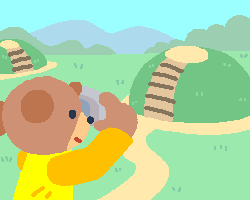
以下は、9月27日(金)に訪れた3カ所の古墳公園の画像及び雑感です。
まずは富士市内の実円寺西古墳公園に行きました。
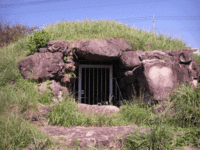
私が昔に通っていた高校の北側です。土地の人的に言うと富士見台の南西位置って言っても良いでしょうか。
こんな古墳が私の生活圏にあった事を知りませんでした。小さいですけど、割と普通の人が古墳と聞いてイメージするカタチそのままの古墳という感じでした。
地元の肩を持つ訳じゃありませんが、そう言う意味では今日訪れた3カ所のうちでは一番良かった気もします。
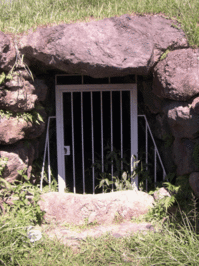
石室の石の積み方が詳細に知れて良かったです。

────────────────────
次に三島市の公園です。向山(むかいやま)古墳公園です。数ヶ月前に出来たばかりだそうで、なるほど真新しかったです。

下の画像の通り、古墳が列を作っています。ちょっとした丘なんですが、多分、標高50mちょっとって所でしょうか。その尾根伝いに作られた古墳群です。

大ざっぱに言って三島大社を南に。伊豆箱根鉄道沿いに2キロ半くらい行った所です。

ここの古墳もやっぱり階段がついていて、上れるようになっています。

一番北側に前方後円墳がありました。下の画像は、後円部分のテッペンです。埋葬の様子の写真を転写した石が設置されていました。

その日の富士山の様子です。ちょうどウマい具合に隠れています。本来であれば正面にそびえているハズなのですが。

天気は良かったんですけどね…。

────────────────────
南にまた3キロほど行きます。函南町(かんなみちょう)の柏谷横穴群(かしやおうけつぐん)です。
もうこの辺になると土地勘ゼロです。そもそも私は三島と函南の境い目すら良く分かりません。

のどかな川沿いをたどってゆきました。

函南町の役場の建物を初めて見ました。

役場の前の交差点です。地図上では読めませんでしたが、実地にて納得いたしました。
そして下が柏谷横穴群です。

広くてきれいな公園でビックリしました。

ヤナギとスイレンです。印象派の巨匠モネも垂涎のデザインになっていました。

岩にボコボコと穴が空いています。横穴群です。
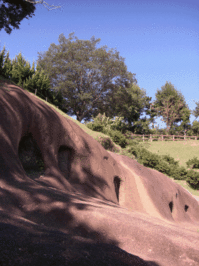
説明文によると、箱根の山が噴火した際の溶岩だそうです。軽石だそうで、柔らかく加工しやすい性質の岩だそうです。しかし風化もしやすいのでモルタルで補強してあります。
つまり昔のままの姿ではないのですね。
昔のままの姿と言えば、本来は石を積み上げてフタをしてあったというので、ポコポコと穴が開いているというモノではなかったと思います。
奥に入って上に登ると、もう少し当時の面影を残しているのかな?という場所がありました。
白い矢印の所にポコッと穴が開いています。

下の写真は別の穴ですが、正面から見るとこんな感じです。葉っぱの感じから大きさが分かるでしょうか。そんなに大きくない開口です。

あった。あった。ありました。こっちの写真が1枚上の画像の開口を正面から捉えた画像です。
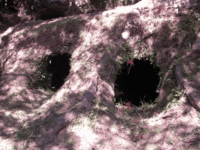
公園内には、竪穴住居の復元モデルなどもありました。

こちらはハニワの馬をかたどった石像のお尻です。

公園を去ろうとしたらちょうど2時。
それに合わせるかの用にしてドコからか音楽のシラべ…。歩みを進めるとなんと、盛装のリスさんが2匹で旋律を奏でていました。
右側のリス氏の楽器は紛失しているようです。

こちらが全景です。良く出来てますね。
(階調を強引に補正しましたので、若干、非現実的なオモムキになっています。)

このほか、写真はありませんが、広い芝生もあって、非常に良い公園でした。近所の人は幸せですね。
この公園から、そう遠くない所に韮山(にらやま)って言う土地もあるんですが、その辺には昔からエラい人が住んでいたようです。古墳なんかもその関係なのでは、というお話でした。
次回は韮山の郷土史料館にも行ってみたいです。
「外出 自転車」カテゴリーアーカイブ
水路をたどりました。

自転車で地元を探索いたしました。テーマとしては治水です。富士市はカタチとしては頂点を上にした二等辺三角形っぽい形をしているんですが、
・西は富士川の反乱に悩まされ
・南側は高波に悩まされ
・東は低地のため水ハケの悪さに悩まされた
非常にザツですが、だいたい以上のような感じみたいです。

今日は東側。浮島沼(うきしまぬま)と呼ばれた地域です。今では単に浮島と言います。富士市と沼津にまたがる広くて平らな土地です。だいたい田んぼ。現在、絶賛刈り入れ中です。
(以下の写真はクリックすると少し大きくなります。)

「沼」って名前の土地は日本中にあると思いますが、今ではほとんど「土地のユーコーカツヨー」ってコトで埋め立てられている昨今では無いでしょうか。浮島もそうです。
(以下の写真2枚は、沼津市内です。)

私は昔の浮島がどれくらいの「沼っぷり」だったか知らずにいたんですが、近所の博物館に通って昔の絵や写真を見ている内に新たな知識を獲得いたしました。
つまり「昔の浮島は沼って言うより、私の感覚だと池に近いダスよ…」という事です。何しろ船が浮いてる写真(グーグル写真検索へのリンクです)が残っています。タマゲました。

沼を埋め立てて、さらに水の量は多からず、少なからず。田んぼに適した状態に制御したいってコトで大変な努力が払われたのですが、その影にドラマありってことで、その辺に非常に興味があります。
現在残っているのはいずれも昭和〜平成の工事された姿なんですが、どっかに当時のヨスガ香るブッケンは落ちてないかしらねぇって期待があったワケですが、難しいですね。やっぱり。
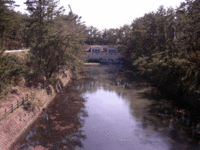
とりあえず今日は1日目ってことでザッと見て帰って来た感じです。実は短パンとモモがこすれるあたりが痛くなって来て退散して来ました。

ビュッフェ美術館に行き、少し斜面を登りました。

私が住んでいる所から、東に30キロくらい行った所にある「ビュッフェ美術館」に行って参りました。いつも通り、自転車です。そんな日記を書いていたのですが、眠くて眠くてしかたありません。おそらく明日、このエントリに加筆する事と思います。興味のある方は、また明日チェックしてみて下さい。
────────────────────
(以下は、加筆分です)
「ビュフェ美術館」の改装が終わって、今日がリニューアル・オープンだと言うので、観に行きました。
ビュフェさんの絵は、生前の母親が好んでおりまして、私が小学生の頃から折に触れて訪れた事のある親しみのある美術館です。
私は正直申しまして、大好きな作家!…という訳でもないのですが、そこはチカラのある世界的な名声のある芸術家の事、原画を見るとウムをもいわさぬ迫力があります。
(以下の写真は、すべて、クリックすると大きくなります。)

この美術館は建物もとても良くて、絵を見せる美術館としてのデザインに優れています。
改修と聞いて、建物自体が変わってしまうのかな、と危惧しましたが、そう言う訳では無くて、あくまで改装工事だったようです。あるいは補強工事なども入ったのかも知れません。
なにしろまだ私が小学生だった頃にできた建物ですから、やはり所々が古くなっていたのは事実です。20年ぶりに地元に帰って来て、ここを再訪した時にはそうした細部も懐かしくて「帰って来たなぁ」なんてしみじみ思ってしまったのですが、あくまで絵を見るための施設ですので、他が妙に目立ってしまっても都合が悪いのかも知れません。
大胆にして細心の異図の感じられる展示。そうした試みができる設計になっているようでした。展示そのものについても緩急が効いていて、物語が浮かび上がっているような構成でした。
おそらく美術館慣れした方にも良い美術館だと感じてもらえる水準にあると感じた次第です。沼津のインターで降りるとそんなに遠くないので、遠方からも人が来てくれると良いなと思います。

丘の下にあるスーパーでパンを買って来たので、外のベンチでパクパク食べました。これから少しこのあたりを冒険いたします。
このビュフェ美術館および周囲の芸術施設群は愛鷹山(あしたかやま)の斜面にあります。富士山に寄り添うようにしてそびえる山です。
通うようになって長いビュフェ美術館ですが、山の奥の方については全くの無知です。ググイと分け入ろうではないかと言うのが、本日の目的のもうひとつなのです。

一応、ネットで得られる地図を印刷して持って来たのですが、山道ですからクネクネしているうちに、現在地を見失う事はお茶の子さいさいです。

結果的には、本来の異図とは違う斜面を登り切った所でギブアップです。道を間違えました。
リカバリーも考えたのですが、恐ろしく良い天気だったのが、一気に曇ってしまい気温は下がり、雨までポツポツと降り出して来ました。
まぁ、最初のアタックですので、しかたがありません。次回に来る時に、本来の目的地と定めていた地までたどり着きたいと思います。
自転車で富士山1周を敢行して参りました。
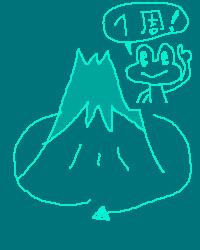
早朝に出発して、1時間ほど前に帰って来たんですが、もう眠くて眠くてしかたがありません。
そんなワケでして、失礼して寝させて頂こうかと存じます。
この日記はおそらく明日、大幅に加筆して生まれ変わる可能性が大でございます。
興味のある方はお手数ですが、また明日、チェックしてみて下さい。「河口湖の水位が下がったと聞くけど本当だった?」というような素朴な疑問をお持ちの方にとっては、多少の実のあるお話も含まれる予定です。それでは失礼いたします。バラサバラサ。
────────────────────

朝の4時半に出発しました。富士宮の市街を抜けたのが6時。
人穴(ひとあな)小学校を越えたあたりの交差点を北上。県道71号線です。
さっき調べてみて初めて知ったんですが交差点を折れた所からが、私は県道71号線の起点だと思っていたんですけど、実は、白糸の滝(しらいとのたき)の手前の松の木とかガソリンスタンドとかコンビニとかがあるあたりが起点でした。そこのコンビニで休憩して朝食を食べたのです。

山梨県との県境を越えたのが8時です。8時半に農協関係のお店っぽい施設がありましたので再び休憩しました。食べ物は少しずつ食べる感じで今日1日を過ごしました。
そのまま県道71号線を進みました。山梨県に入っても道の名前としては71号線です。番号が変わらないように合わせてあるんでしょうか。でも混乱しなくて良いなと思いました。
途中で本栖湖(もとすこ)を展望する駐車場を通りかかりました。ここで初めて71号線が通っている地点が、かなり高い場所にある事に気付かされました。湖面がかなり下に見えます。どおりで苦しい訳です。国道139号線を通るより距離は短くなりますが、その分、少し登る事になるみたいです。
その後、突き当たりの交差点で国道139号線に合流しました。鳴沢村(なるさわむら)です。
小学校がありました。運動場からにぎやかな声が聞こえて来ます。見てみると、リレーの練習をしているようです。バトンの受け渡しが難しいみたいで苦労する子供たちを見ました。
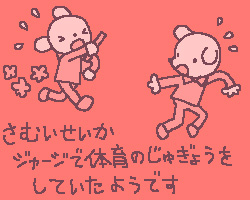
それにしても道が狭いです。片側1車線で追い越し禁止の道路を大きなトラックがバンバン走っています。かなり危ないので、ずっと歩道を気をつけて走りました。
ところが、9時半くらいに河口湖町に入ったあたりで急に道幅が広くなって、穏やかな印象に一変しました。
歩道も広くなったので、そのままのんびり走ります。本日の平均時速は10キロちょっとでした。これは自転車としてはかなり遅いのですが、私にはこれくらいがちょうど良かったようです。
歩道を走っていたら、自然に河口湖の方角に招かれてしまいました。流れ流されて気が付けば河口湖が目前です。大きいですね。
寄り道する体力的な余裕は無いと考えていたので、富士五湖鑑賞は避けるつもりでしたが、しかたがありません。階段を下りると湖を周遊する道路に出られそうだったので、自転車を担いで湖に出てみました。
とても天気が良くて、風も無いし、穏やかな気分がします。湖も、その向こうに見える山々も、とてもきれいです。
ふと「河口湖と言えば、水位が下がってしまって、お堂への地面がむき出しになっていると聞いたけど、それってどこだろう?」と思い、左側を見たらそこには、ニュースの映像などで見た、本来であれば湖上に位置すると言うお堂が見えました。あまりにあっけないですが、探す労力が省けて助かりました。
その後、国道139号線に戻って適当なコンビニでまたもや休憩。パンなどを食べました。11時ちょっと前です。
富士吉田市に入ると、国道139号線に別れを告げる交差点がやって来ます。139号線は、北上して大月市と言う所につながります。実はこの139号線って富士市民としてもとても馴染みのある道で、富士市の港の付近を振り出しにグイグイ登って行って、富士宮を更にグイグイ行って富士山を半周する形で山梨県に突入して、最後には上で申し上げた通り大月市に到着するのです。そんなことから地元では通称”大月線”って言います。いつか、この道をたどって大月市まで行ってみたい物です。あんまり私の地元の人で大月市までわざわざ行った事のある方っていないと思います。
「大月線通って大月市まで行ったですよ」なんて言うと話のタネになりそうな気がします。
しばらく走ると、山中湖です。あんまりおおっぴらに入ったらダメそうな別荘地を、失礼して走りました。
ここまで割と平坦な道でしたが、ずっと登りです。目指すは籠坂峠(かごさかとうげ)と言う山梨と静岡の境界に位置する高い場所です。けっこう覚悟していたのですが、別荘地を抜けた場所がすなわち最高点で、あとは下るばかりでした。ここで12時半でした。

しかしこの下りがまた大変で、1番の緊張でした。すごい下りでカーブは多いし、すぐ横は斜面で転がり落ちたら死んじゃいます。それと強風が凄くてハンドルが揺れるほどです。
この強風は結局この先、御殿場の自衛隊の演習場を抜けるくらいまで続いて厳しかったです。下りなのにペダルを懸命に廻してもなかなか進まないと言う苦難の連続でした。
2時くらいに裾野市の須山(すやま)にあるコンビニで休憩して、最後の難所の十里木(じゅうりぎ)までの上り道に臨みました。
朝のうちから、はやる気持ちを抑えるようにして極力遅く走って来たのは、すべては最後にあるこの登りのためだったんですが、やっぱりとてもキツくて大変でした。
そんなこんなで帰宅したのが午後の4時ちょっと過ぎです。ほぼ12時間かかりました。

御殿場を抜ける際に、去年に間違ってクサカベ絵の具の工場まで行ってしまった時に発見した裏道を利用しました。そんなに特徴のある道でもないので、うまくたどれるか自信がありませんでしたが、無事に通過出来ました。
前もって立てておいた計画通りにコトが進むなんて、私には珍しかったです。小さな公園で幼稚園くらいの子たち数十人が遊んでいました。ほぼ同数のお母さんたちもいました。幼稚園の新入生歓迎の遠足だったのかもしれないと思いました。
上の写真は、富士市からの富士山です。「富士山こどもの国」と言う施設の脇の林道から撮影しました。




