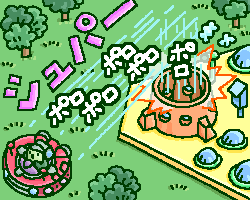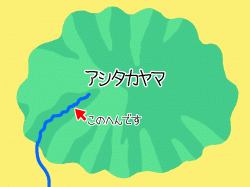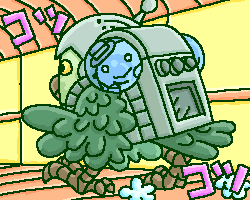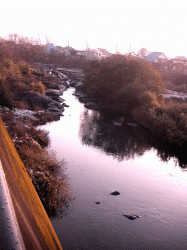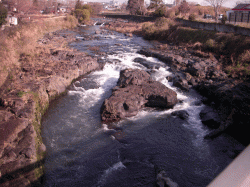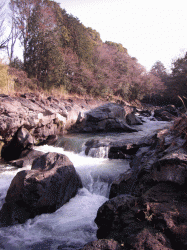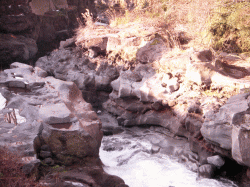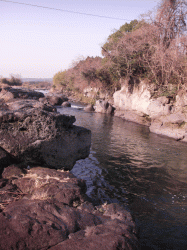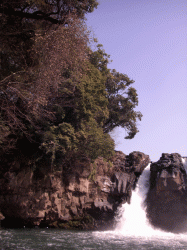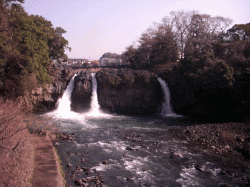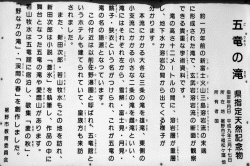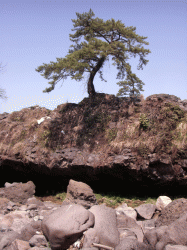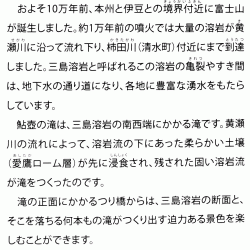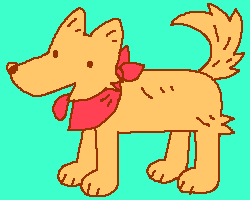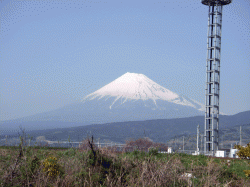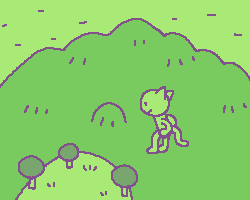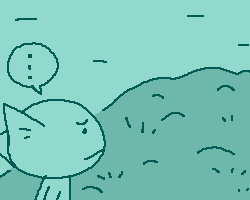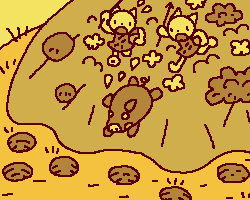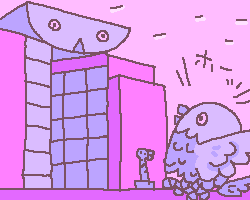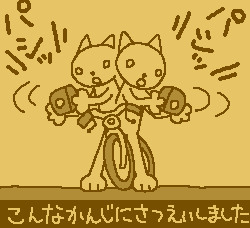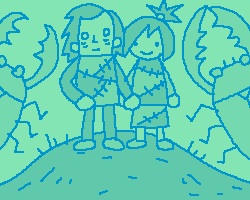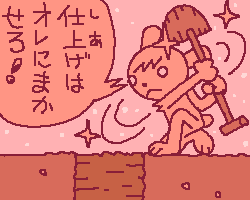市内にある滝に行きました。
きのうの富士山はこんな感じでした。雲にかくれてほとんど見えません。
(本日の写真も、クリックすると大きくなります)
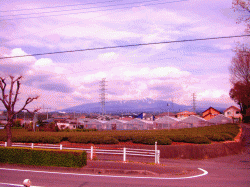
────────────────────

愛鷹山(あしたかやま)にやって来ました。
今まで、沼津サイドの愛鷹山を調べて来ましたが、富士市サイドの愛鷹山も見てみよう!というワケなのです。
写真の奥、ヤマヤマ全体が総称としての愛鷹山です。峰のそれぞれに個別の名前もあるのですが、登山する人でもない限り、その名を使う人はいない感じです。
滝を目指して、写真の左奥の方に進みます。
高い所を通っている道路は、新東名高速道路です。
初めて通る道を進みましたが、ほどなくして通行止めのサクに行く手をさえぎられました。舗装も途切れてジャリ道です。自転車を押して進みました。
アセをかきつつ進むと、いつの間にか、かなり高い所を歩いていました。

(上の写真は方角的に言いますと、来た道を振り返った感じです。下に見える道が、本来、普通に使われる滝までの道です。奥の方は色調が飛んでしまっていますが、海です。)
下の写真の通りのジャリ道ですが、将来的には舗装するつもりも見て取れました。

2キロくらい歩いた所で、ようやく既存の舗装道路に合流しました。
更にしばらく行くと大きな橋があります。

これが我が富士市の誇る滝。「大棚(おおだな)の滝」なのです。

帰りは違う尾根を下りましたが、かなりの急角度でした。

立っているのがちょっと大変なくらいです。
実は富士市サイドの愛鷹山からは、旧石器時代の遺跡がほとんど見つかっていません。(古墳などはあります。)
ゆるやかな沼津サイドと違って、尾根の幅が狭く、角度も急なので利用が難しかったようです。私も納得しました。この1カ所だけ見て全部を判断する事はできないのですけど、辺りを見回してみても、だいたい似た稜線をしていました。
────────────────────
先日、近くの博物館に行きましたが、そのサイに興味深い写真を見ました。
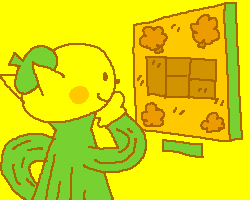
市内の浅間(せんげん)神社を統括していたという古いお寺の敷地の跡の写真でした。名前を「東泉院(とうせんいん)」と言います。
写真の感じから、だいたいの位置の見当がついたので、ついでにソコにも行きました。
吉原公園と言う場所です。

すると今まさに工事中でした。どうやら公共施設として整備されるようです。ちょっと早く来過ぎてしまいましたね。

楽しみですね。
────────────────────
全部で10キロちょっとの道のりだと思いますが、坂が多くて大変でした。
良く使われる道を素直に使えば、楽に行けるのですが、尾根の様子も知りたかったので、大変な道のりになりました。
しかしこれで愛鷹山の調査もほとんど終わりです。残りは1回程度です。