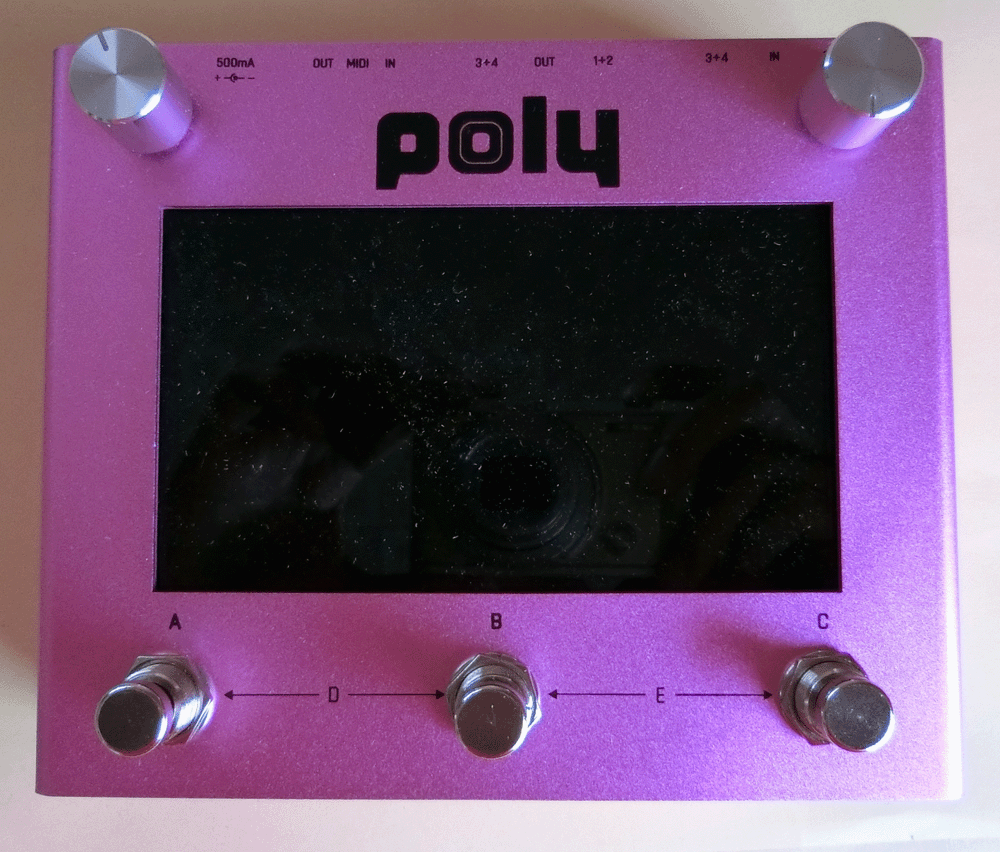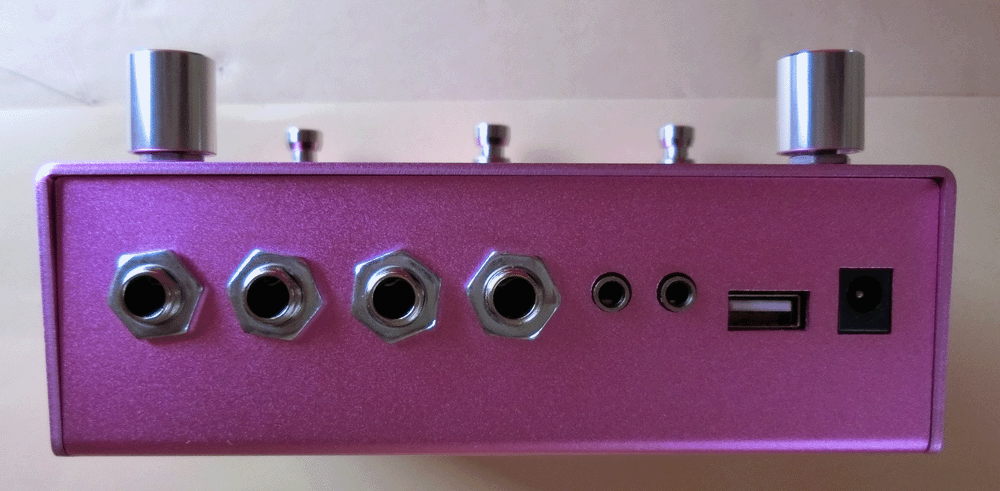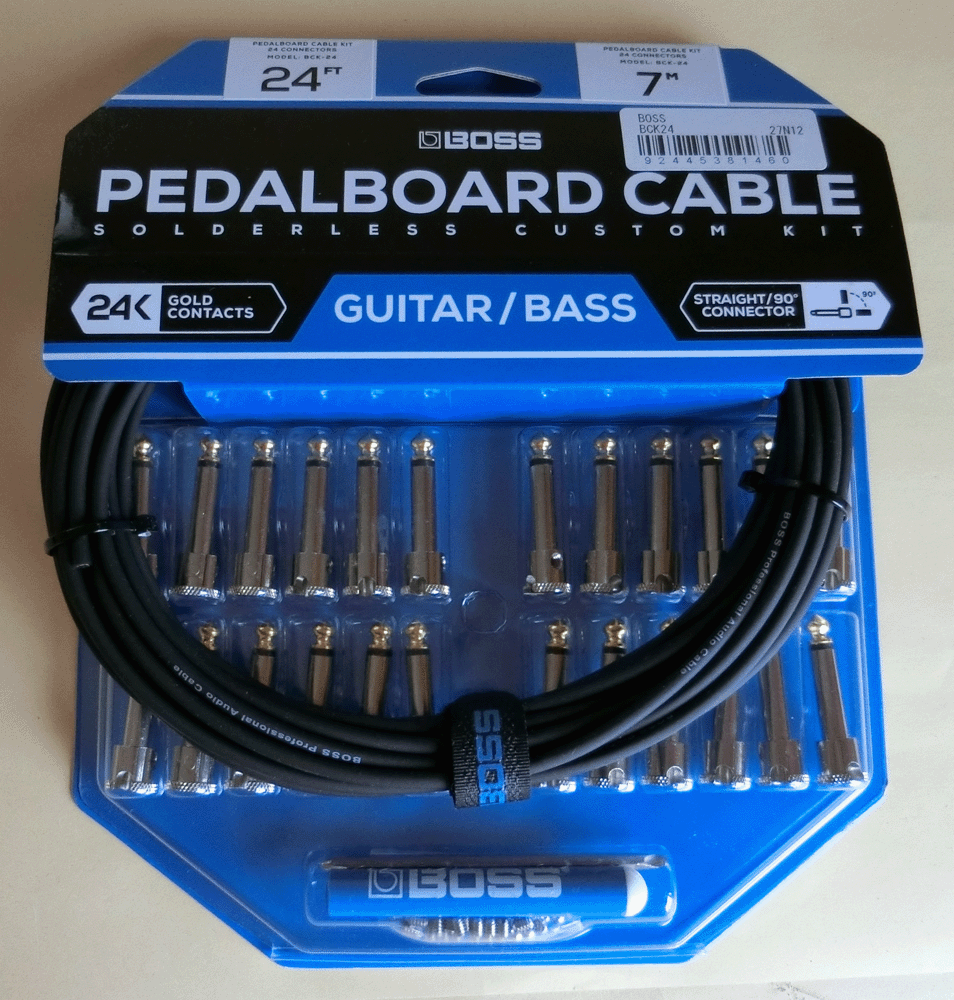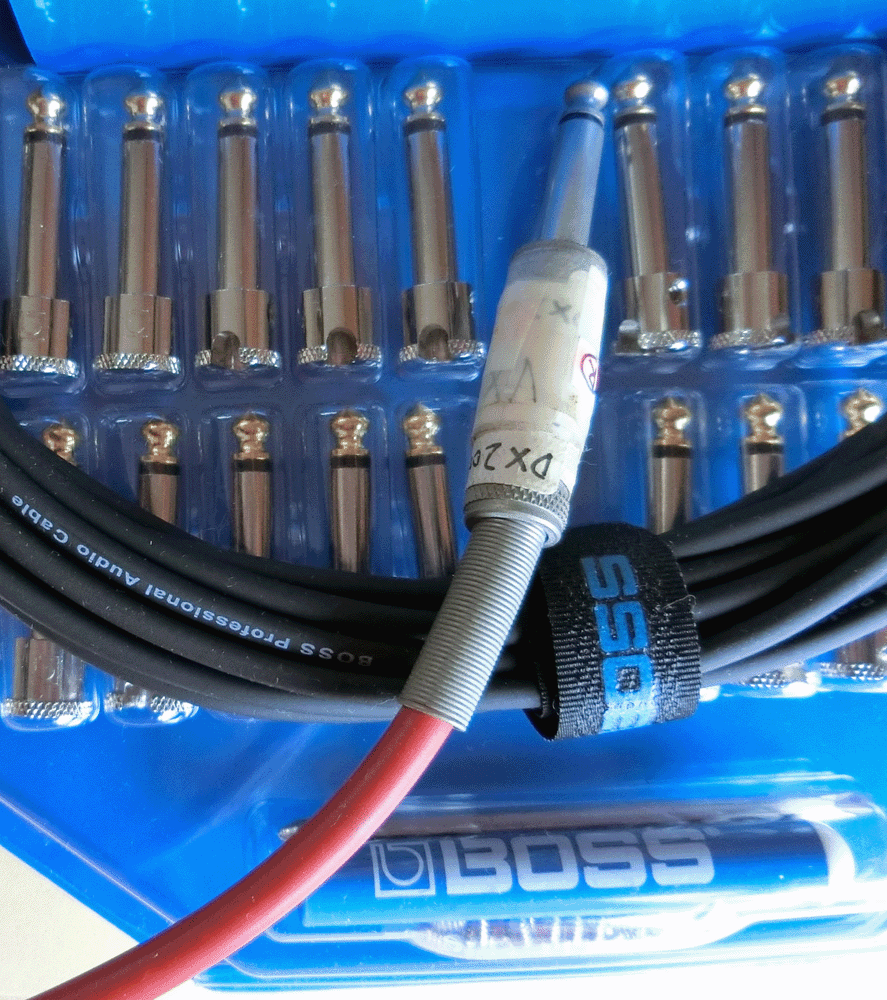2025年3月19日
【エフェクター環境の進捗メモ(マルチエフェクター編)】

小さなマルチエフェクターを購入しました。
先ごろ変なエフェクターを入手した私ですけど今回のはかなりちゃんとしたエフェクターです。
こいつに関しては「絶対に使えるし役に立つ」という確信がございます(逆に言いますと前回のピンク色のエフェクターは「正直どうなんだろうか?」って気持ちが拭えません)。
戻します。今回購入した小さなエフェクターに。すでに導入済みの大きなマルチエフェクターを補助させるという位置付けなのです。
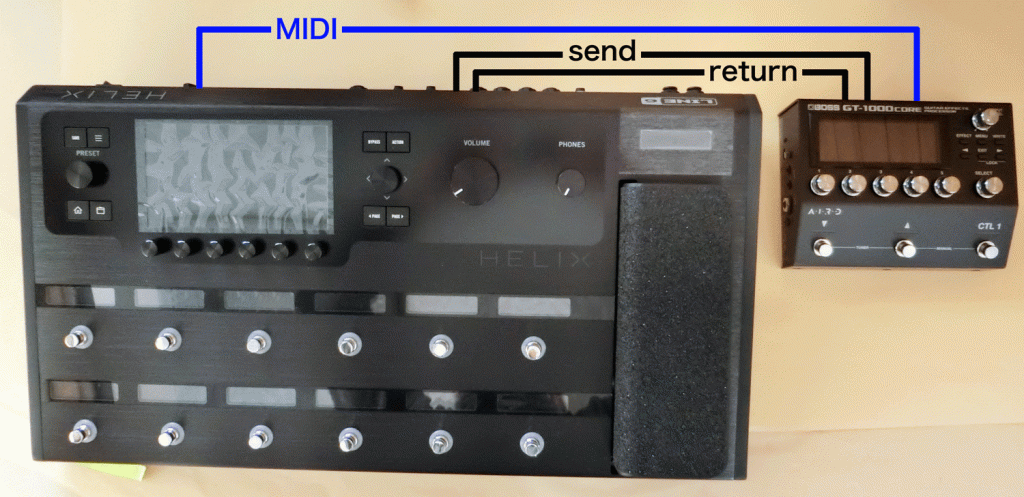
上掲したお写真のような感じです。この2台に限らず手持ちのエフェクターは全部つなげるつもりでいます。
具体的には音声経路を接続するわけですが、制御信号(MIDI)も接続した上、連動させようと思います。
そうすることで複数台をあたかも1台の機械として扱えるのです。
完全に同体にはなりえませんが、処理能力については倍増します。
より複雑なエフェクト効果の作成が可能になります。
複雑なエフェクト効果を作ろうと思うと1台のマルチエフェクターでは能力的に足りなくなることがありますので回避策です。
現実問題としては1台だけで済む音色が大半ではあるんですが、ここ一番っていうときにせっかくの着想を機械的な限界によりあきらめるのも残念です。もう1台足しておけば安心かなってことなのです。
昔に比べれば今のエフェクターの処理能力ってすごいですけど、同時に内包するエフェクト効果のひとつひとつが要求する演算量も時代が進むにつれて増えています。結局のところ、いつになっても過度なエフェクト効果を求める人は複数台を組み合わせるべきなのかなっていうのが現状における私の見解です。
× × ×
以下に具体的なことを少しだけ記述します。
例えばトーンを大きい方で作って空間系は小さい方に任せるとかです。
空間系というのは“響き”のことです。お風呂の中は音がよく響くとかああした音環境を機械的に再現する感じです。
多くの演算量を必要とする空間系エフェクトですが、必要とする組み合わせみたいなものはおおむね決まっていますので、まずはそっちをラチ外に置き、トーンの面で試行を重ねる。満足したところでその後段に空間系を置くみたいな。増大する演算量を気にせず冒険できそうです。
別の考えとしましては、音声を分岐させてそれぞれ別のタイプの音を分担し、最終段でミックスするなどです。
下の画像は“信号を分配する”っていう書き方がイマイチ、ピンとこなかった場合の参考用に掲載いたします。今回導入したエフェクターのエディット画面のひとつであって、説明途中の複数台における分岐を表すものではないのですが、1枚のスクリーン画面上にわかりやすくまとまっていると思います。これで「なるほどこういう分岐なのか」ってなれば良いのですけど。そんなにむずかしいことを言っているわけではないのだなと納得いったでしょうか。
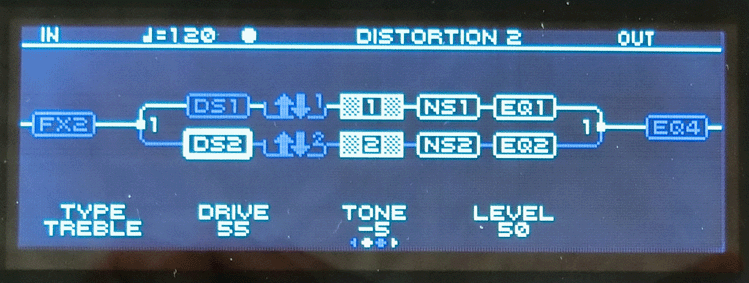
“分岐”ということで申しますとチャンネルディヴァイダーをかませて帯域ごとの処理みたいなこともできるのだそうです。楽しそうだと思います。録音エンジニアの人たちが行う処理に近づけそうです。
あるいは3ヶとか4ヶといった複数の音色を作っておき、いつでも任意の音色が出せる状態にしておいてスイッチで選択できるようにしても良いかなと思います。もしかしたらこれが一番実践的かもしれません。
ギターシンセも導入しましたのでより多くの選択肢を持てそうです。
ひと昔前のマルチエフェクター事情であれば音色変更にはプログラムパッチを切り替えるしかなくて、この場合の切り替えってつまり音色設定をロードする時間が必要ということであってタイムラグがさけられない非情な現実でありました。音色をパカパカ変えたいギタリストは身もだえしていたと想像しますけど、あらかじめ全部の音色が出来ていてスイッチでオンオフするだけなら、これは瞬時にできちゃいます。
私の音楽的な出自であればUK82なハードコアパンクのヒズみきったサウンドとピコピコしたシンセサウンドを行きつ戻りつという可能性です。いかにも便利そうです。その反面わざわざそんなことしたい人の数っていうのも相当に限られるだろうなって部分がまた良いのではないか。
× × ×
エレキギターの音色をパカパカ変えるっていうのは一貫性はもちろんありませんが、ニューウェイヴ的ではあるなと思うんですよね。
イギリスのニューウェイヴなロックバンドであったXTCのかつてのライブ演奏におけるデイヴ・グレゴリーさんの場合、エレキギターからシンセサイザーへと忙しそうでした。参考動画としては「XTC – Generals and Majors live」もしくは「XTC – No Language in Our Lungs live」などです。しかし数十年を経た今なら足元のスイッチを踏むだけでギターから手を離さずに同じことができます。
× × ×
現状において変なことをしたいであるとか複数の音色を操りたい、しかもそのシステムを容易に持ち運びたいとなると複数台のマルチエフェクターを組み合わせてひとつの音声処理工場として使う形態が最適解であろうと思います。もちろん実際に運用するにおいては決して良いことばかりではないのですけど。
× × ×
今回導入したエフェクターは同社が作る既存機種の中枢を抜き出したものです。
80年代ニューウェイヴで聞かれるギターサウンドであれば今回導入したこの小さなエフェクター1台でも作れます。つまりそれを乗り越えたいんですよね。
音作りとしてはパソコンにつないでエディット作業できますので素早くプログラミングできそうです。老い先みじかい私にピッタリ。
下の画像の左下の方にUSBケーブルを挿すところが見えてます。ここでパソコンとの情報をやり取りするらしいのです。最近ではこういうのがけっこうあるようです。便利ですよね。

以上、今回導入したマルチエフェクターで私が「こうしたいな」と企画している事柄その他についてのご説明でした。
───────────────
色々と買ってきましたが構想していたエフェクター類の購入はこれで完了です。
1年ほどかかりました。
自分で言うのも何ですけど、ここまで買い揃えてきたエフェクター群の組み合わせは非常に大きな可能性を具現化したものです。
見掛け倒しにならないようにしたいですけど、これ見よがしなグレートな音を出したいわけでもありません。
私はこれまで35年以上の大変に長く貴重な時間をシンセサイザーやらエフェクターやらをいじることでドブに捨ててまいりましたが、そこで終わってしまっては悲しいので何か残したいと願っています。
その場その場の表現したい音世界を反映させうる土台として機能してくれれば、という気持ちです。
機械は機械。しかし1+1が2以上になりうるのが音というものを触っていて面白いなと思える瞬間です。耳は騙されやすい。しかしそこからくる桃源郷であったりの広がる目に見えない風景は音を聞くことからでしか、なしえません。
音を構成する要素は、時間軸上における変化であったりいくつかあると思いますけど、各部位に対して意図ある音を作りたいです。
単純な意図の集合体だとしても方向性に齟齬がなければ、それらいくつかが組み合わさることでけっこう味わい深いものになるのではないかと思っています。
試行錯誤をむしろ喜びに変えて仕上げていきたいです。
残り時間が少なくなってきた私の人生ですが納得のいく音をひとつでも多く残せれば機材に投資した意味も出てくるでしょう。
願わくば故・湯浅譲二さんの言葉にある「未聴の宇宙」ですよね。
小学校の6年間を湯浅さん作曲の校歌を歌うことで湯浅ワールドに親しんだかもしれない私ですので、人生の最初の方と最後の方をくっつける意味でも「未聴の宇宙」にはちょっとこだわりたいです。
湯浅さんが言うコスモロジーが私にも備わっているとすればそれらを全部かけて音に取り組みたい。年齢を考えるに、もう今しかないだろうなという気持ちです。