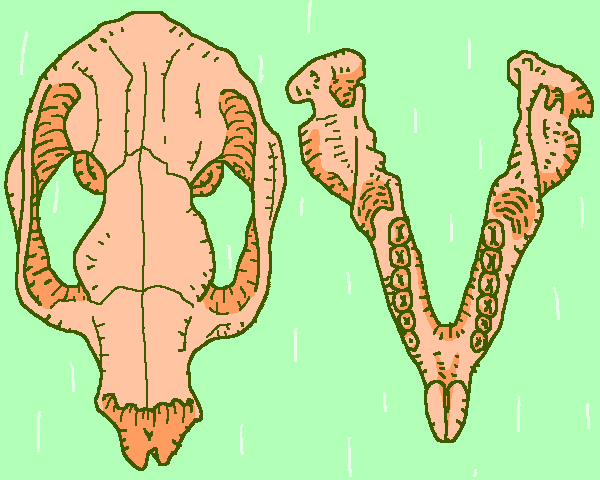
コアラさんの頭蓋骨をじっくり見る機会を得た上でのイラスト作成なんですけど、ビックリするのはアゴの骨の上の方が頭蓋骨の目の裏の空洞に収納されているらしいというその構造ですよね。そんなことあるんだとおどろきました。他にもこうした構造を持つ動物っているんでしょうか。気になります。
───────────────
日記的な記述です。
たくさんラジオ番組を聞きました。
今の私はブログ用イラストの量産作業をしておりまして、ずっと机に向かっている都合上、多くラジオを聴く時間が発生するのです。
今はNHK・FM「クラシックの迷宮」を聴き終わったところです。萩原哲晶(はぎわら・ひろあき)さんの生誕100周年を記念する番組。クレージーキャッツのヒット曲における作曲と編曲で知られる方。東京音楽学校の出身であり、戦中は陸軍戸山学校の軍楽隊に居たと知りました。
クレージーキャッツの楽曲における縦横無尽な音楽的要素のひしめくサマとか行進曲とかは軍楽隊での経験とキチンと音楽を学んでいたからこそっていうのがあったんだなと理解しました。
それと悪の放送番組である「ジャズ・トゥナイト」を「聞き逃し配信」にてギル・エヴァンスさんを取り上げた2時間の再放送を聞きました。晩年の時期よりそれ以前のお仕事が良いなと感じました。
以前にマイルス・ディヴィスさんの「クールの誕生」のアレンジをジェリー・マリガン氏とともに手掛けたと(もう一名いたとも思いますけど)知ったんですけど、それからずっとデイヴィス氏との作業は続いていたと知りました。長い仲ではあると思っていたんですけど、もっと深かったみたいです。
その中でモード・ジャズを作り上げていったとかそんな感じ。
ギル・エヴァンスさんはローランド・カークさんの最晩年でのコンサートでエレピで伴奏している映像をネットの動画サイトで見たことがありましてどっちも互いに上行するフレーズでしたかね。このままだとぶつかるぞって時に即座に手を休めて回避。しかし手は打ってありましてエレピを優しく弾いた時の打鍵感ゼロで音程だけがフワ~って浮き上がってきてカークさんのソロをまたしてもうまくサポートみたいな局面に感動しました。それ以来エヴァンスさんは主役を立てるすごくいい人だって思ってるんですけど、音楽的な知識と人格が揃った人だっていう結論に及びました。デイヴィス氏とずっとやれたんならなおさらだと思います。
同じくNHK・FMにて「世界の快適音楽セレクション」をききました。本日のテーマは「giveの音楽」。選曲家は湯浅学さんでした。
最後の方で聞いた「Los Pirañas – El aguazo de Javier Felipe(ハビエル・フェリペの豪雨)」ですけどこれはヤバかったですね。クンビアでスティーヴ・ライヒっぽいことをやるみたいな。野太い低音と絶え間なく続くミニマルフレーズに唸りました。興奮しました。素晴らしかったです。
あとは日本の方々で初めて知りましたが「CaSSETTE CON-LOS – フランク・シナトラ」。良かったです。録音の質感も古いラテン音源みたいなものに近づけてあったみたいでスキがないなと感じました。
あとは「The Residents – Give It to Someone Else」。先週に続いてゴンザレス三上さんによるご自身の楽曲制作上での困難にぶち当たった時のレジデンツ聴取が救いになっているというイイお話、その詳細なんかも聞けました。ひょっとしたら三上さんくらい真剣にレジデンツを聞いている人も珍しいのではっていう気もします。
───────────────
そんなわけで私も「giveの音楽」を選曲したんですが夜も10時を回った現在でございまして私はもう眠いので簡潔に行きます。
ホントは他にも何曲か選んだんですけど仕方ないのです。
「Los Iniciados – Todo Ubú_Presentacion Del Príncipe Freixinet」です。83年の作だと思います。バンド名は「入信者」っていう意味らしいです。実態としてはAviador Droっていうスペインはマドリッドのバンドの別プロジェクトなんだと思います。70年代末からたぶん今に至るまで続く活動。長いんですけど創作欲の濃さっていう面でも稀有なバンドっていうか中心人物の”業”がよほど深いんだと思います。
簡単に言うとスペインのディーヴォかなって思うんですけど、上掲楽曲を聴いた印象からも感じ取れると思いますが不気味で可愛らしいというレジデンツにも通じる部分があるなって思います。この他にもエジプトのミイラっぽいバンドもやってたはずです。思いつくと短期間にドドドって感じに曲を作る人じゃないかと想像しています。イキオイ重視でクオリティも大外しはしないけどまぁそれなりのものが混じっていても気にしないって感じですかね。
以前に「メキシコのシンセポッパーズは言語が共通するスペインのシンセポップをよく聞いていてライブでカバーしている例をよく見る」みたいなことを書いたことがあったと思うんですけど、まさにこのAviador Droはかなり愛好されていた形跡がハッキリと確認できます。
私のシンセポップ探査活動においてはスペインのシンセポップも幾つかまとまってきておりまして、そうしたモロモロをいつか紹介できると良いなって思います。
もう眠くて起きていられない感じですので本日はこの辺で。どうもありがとうございました。